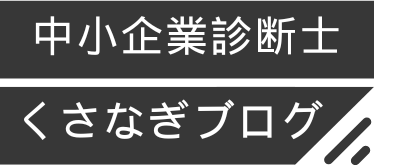財務分析を「やる意味」を変える
財務分析なんて、やっても意味がない。
そう感じている経営者は、意外と多いのではないでしょうか。
「数字を見ても売上は上がらない」「机上の話だ」と。
しかし、実際の現場でたくさんの企業を見てきた中で、私は断言できます。
財務分析をしていない会社に、偶然の成長はあっても、再現性のある成長はない。
財務分析とは、決算書を読むことではありません。
「数字の裏にある経営の行動」を読み解くことです。
たとえば、利益が出ているのに現金が減っている会社。
これは「儲かる仕組み」はあるのに、「お金の回し方」が間違っているというサインです。
つまり、財務分析とは——
経営の健康診断であり、次の一手を導く経営の言語です。
数字を「評価」ではなく「意思決定の材料」として見られるようになったとき、
経営は、感覚から戦略へと変わります。
経営の現場を動かすのは、感情でも理論でもなく、数字の意味を正しく理解する力です。
これが「財務分析をやる本当の意味」です。
Ⅰ.財務分析とは「経営の現在地」を知るツール

1.誰のために財務分析をするのか
財務分析には、見る人の立場によって目的が異なります。
経営者にとっては「課題の発見と改善のため」、
金融機関にとっては「融資判断・信用維持のため」、
投資家にとっては「成長性や再建可能性を見極めるため」です。
中小企業診断士としての立場で言えば、
財務分析の目的は「経営者の意思決定を支えるため」。
つまり、数字を「評価」ではなく「行動の起点」として使うことにあります。
数字を通して、過去の意思決定の結果を客観的に確認し、
次にどんな一手を打つべきかを考える。
これが真の財務分析です。
2.財務分析は外部環境・内部環境と一体で考える
財務分析は、単に損益計算書や貸借対照表の数字を比べる作業ではありません。
3C分析(顧客・競合・自社)やSWOT分析(強み・弱み・機会・脅威)など、
外部・内部環境と組み合わせてこそ意味を持ちます。
数字は、経営環境の「結果」であって「原因」ではありません。
「なぜこの数字になったのか」「背景に何があったのか」を探ることで、
初めて経営の「本質的な問題」にたどり着くのです。
3.分析の本質は「結果と行動の関係性」をつかむこと
売上の減少、利益率の低下、借入金の増加——。
これらは「結果」にすぎません。
分析の目的は、「結果を変えるにはどんな行動を変える必要があるのか」を考えること。
財務分析とは、数字を眺めることではなく、
行動を変えるための手がかりを見つけることなのです。
Ⅱ.中小企業における財務分析の勘所
1.企業ごとに「健康状態」は違う
平均値や指標の標準値に惑わされないこと。
財務分析でよくある誤解は「業界平均が基準になる」という考え方です。
しかし、企業の経営状況やビジネスモデルは千差万別。
たとえば、在庫を多く抱える業種と受注生産の業種では、
同じ「回転率」の数字でも意味がまったく異なります。
分析は「平均」との比較ではなく、
その企業の「あるべき姿」とのギャップを確認することに本質があります。
2.数字は「経営の言葉」である
決算書の数字は、経営者の意思と行動の記録です。
新しい設備を買った、社員を増やした、価格を下げた——
すべての意思決定が、数字に姿を変えて表れています。
数字を読むということは、経営者の意思決定をもう一度トレースすること。
数字を「経営の言葉」として扱えるようになると、
財務分析は単なる作業から「対話のツール」に変わります。
3.分析の視点は常に未来に向ける
財務分析を「過去の採点」として捉える人もいますが、
それは半分しか合っていません。
正しい財務分析は、「未来の経営方針を考えるための準備」です。
数字の変化を「兆し」として捉え、
次の期に何を変えるべきかを見極めることが本質です。
つまり、財務分析の視線は常に過去ではなく未来にあります。
弊社代表が立ち上げた株式会社CONVYでは、財務分析から未来を作るため事業計画の策定支援と、WEBマーケティングによる売上拡大の伴走支援までを一気通貫で提供しています。先着3社限定で無料コンサルティングを受け付けています。
お気軽にご相談ください。
中小企業診断士が代表のWEBマーケ専門会社CONVYに相談する
Ⅲ.財務分析の流れと4つの基本視点

1.分析の流れ:現状把握→課題発見→対策立案→実行
財務分析のゴールは「課題を見つけること」ではありません。
その先の「改善行動」までつなげることです。
経営は「計画→実行→検証→改善」のサイクルで回っています。
財務分析はその「検証と改善」を担う部分。
数字を見て終わりではなく、行動を変えるための出発点なのです。
2.4つの基本視点
財務分析には、4つの代表的な視点があります。
それぞれの数字は独立して存在するのではなく、
互いに影響し合う関係性を持っています。
| 視点 | 内容 |
|---|---|
| 収益性 | 利益の構造を理解し、儲かる仕組みを分析する |
| 効率性 | 資産をどれだけ有効に使えているかを測る |
| 生産性 | 人・設備・コストをどれだけ活かせているかを見る |
| 安全性 | 会社を支える「守り」の力を数値で確認する |
主な経営指標と公式(概要)
| 視点 | 指標名 | 公式(基本形) |
|---|---|---|
| 収益性 | 売上高総利益率(粗利率) | 売上高総利益 ÷ 売上高 × 100 |
| 売上高営業利益率 | 営業利益 ÷ 売上高 × 100 | |
| 売上高経常利益率 | 経常利益 ÷ 売上高 × 100 | |
| 総資本経常利益率(ROA) | 経常利益 ÷ 総資本 × 100 | |
| 自己資本利益率(ROE) | 当期純利益 ÷ 自己資本 × 100 | |
| 効率性 | 総資本回転率 | 売上高 ÷ 総資本 |
| 売掛金回転期間 | 売掛金 ÷ 売上高 × 12(ヶ月) | |
| 棚卸資産回転期間 | 棚卸資産 ÷ 売上原価 × 12(ヶ月) | |
| 有形固定資産回転率 | 売上高 ÷ 有形固定資産 | |
| 生産性 | 労働生産性 | 付加価値額 ÷ 従業員数 または 付加価値額 ÷ 人件費 |
| 付加価値率 | 付加価値額 ÷ 売上高 × 100 | |
| 資本生産性 | 付加価値額 ÷ 総資本 | |
| 安全性 | 自己資本比率 | 自己資本 ÷ 総資産 × 100 |
| 流動比率 | 流動資産 ÷ 流動負債 × 100 | |
| 当座比率 | 当座資産 ÷ 流動負債 × 100 | |
| 固定長期適合率 | 固定資産 ÷(自己資本+固定負債)× 100 | |
| 負債比率 | 負債 ÷ 自己資本 × 100 |
詳しくは明日以降の各記事で、それぞれの指標の意味・使い方・改善の考え方を解説します。
Ⅳ.財務分析とどう向き合うか
1.財務会計から管理会計へ|分析は「行動のため」にある
多くの中小企業では、財務会計(外部報告)に留まっています。
しかし本当に必要なのは、「管理会計」への転換です。
つまり、決算が終わった後に「見る」数字ではなく、
経営の意思決定に「使う」数字をつくること。
分析とは、過去を整理することではなく、未来を設計するための行為です。
2.単品管理の重要性
特に製造業や小売業では、「単価」「数量」「原価」を単位ごとに把握することで、
会社の強みと弱みが一気に見えてきます。
一見地味な作業ですが、単品管理を導入した企業は、
利益構造を言語化できるようになり、経営判断が劇的に変わります。
数字は経営文化を変える力を持っているのです。
3.未来を変える「数字との向き合い方」
数字を見ることを「評価」と捉えるか、「成長の材料」と捉えるか。
その意識の違いが、会社の成長スピードを左右します。
数字は冷たく見えて、実は経営者の努力と想いの結晶。
数字に「温度」を感じ取れるようになったとき、
経営者としての視野が一段広がります。
Ⅴ.まとめ|財務分析は経営改善の出発点
財務分析とは、経営者の直感を数字で裏づけ、
行動を導くための羅針盤です。
財務分析をしない経営は、地図を持たずに航海するようなもの。
数字を恐れず、数字と対話しながら経営を進めること。
それが「数字に強い経営者」への第一歩です。
明日からは、4つの視点のうち「収益性の分析」をテーマに、
具体的な見方と改善の方向性を解説します。
次の記事:「中小企業向け 財務分析|収益性の分析と改善のヒント」