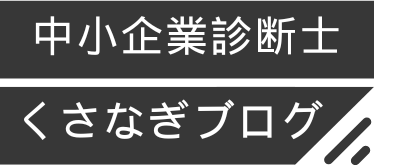〜信頼と成長を支える姿勢とスキルアップ〜
はじめに
中小企業診断士の仕事は、経営と数字を扱う専門職のように見えて、
実は「人と人との信頼」を土台に成り立っています。
企業の課題を分析し、改善策を提案するだけならAIでも可能な時代になりました。
だからこそ、診断士に求められるのは「人の心を動かす力」であり、
経営者の想いを理解し、共に未来を描く姿勢です。
私はこれまで多くの企業支援を通じて、
「聴く」「考える」「伝える」「伴走する」ことの重要性を痛感してきました。
本記事では、中小企業診断士として私が大切にしている
姿勢・考え方・スキルアップの方法を、実例も交えながら整理します。
Ⅰ.中小企業診断士の役割は「分析」から「助言」へ

1.支援法改正で変わった診断士の立ち位置
2000年の「中小企業支援法」施行は、診断士制度の大きな転換点でした。
それまでの「中小企業指導法」では、行政が上から「指導」するスタイルでしたが、
改正後は、「民間の力を活用する支援」へと方向転換しました。
つまり、診断士は公務員的な存在から、
民間コンサルタントとして中小企業の伴走支援を行う専門家に変わったのです。
この変化によって、求められる役割は「診断」から「助言」へとなり、
過去の財務分析のみならず、企業が将来「直面することが予想される課題を明らかにし、事前に対処方針をアドバイスする未来に向けた戦略構築や意思決定支援が強く求められるようになりました。
2.現代の診断士に求められる3つの力
- 分析+助言力 問題点の抽出に加え、実行可能な改善策・成長戦略を提示する力。数字だけでなく、経営者の価値観・現場文化も踏まえて考える必要があります。
- 構想力・創造力 答えのない状況でも、自社の強みや市場の変化から「未来の形」を描く力。情報が不完全な中でも仮説を立て、検証し、修正していく柔軟性が求められます。
- メンタリング力 経営者の意欲を引き出し、自ら考え行動できるよう導く力。ときには精神的な支えとなり、長期的に信頼を築く姿勢が欠かせません。
診断士は「経営を診る人」ではなく、「経営者と共に未来を創る人」。
Ⅱ.信頼関係がすべての出発点
どんなに正しい分析でも、経営者が心を開かなければ意味がありません。
コンサルティングの成果は、提案内容の質ではなく、信頼関係の深さに比例します。
1.信頼を得るための準備と姿勢
支援の成否を分けるのは「最初の1時間」です。
最初の訪問で「誠実さと理解力」を示せるかどうかが、今後の関係を左右します。
そのために必要なポイントは以下の3つです。
- 徹底した事前準備:業界動向・3期分の決算書・人員構成・経営者経歴を把握
- 傾聴姿勢:途中で話を遮らず、要約と確認を繰り返しながら聴く
- 共感と観察:表情やトーンの変化から「本音」を感じ取る
社長の言葉の裏にある「不安」や「本当の課題」を見抜くことが、信頼構築の第一歩。
2.提案は「現場目線」で具体的に
理論だけでは会社は動きません。
同じ「在庫削減」という提案でも、製造業と飲食業では方法もタイミングも違います。
大切なのは、「実行できるレベルまで具体化する」こと。
社長が「これならできそうだ」と思える現実的な提案を出すことで、次の行動につながります。
社長よりも深く自社の課題を考える姿勢が、「またお願いしたい」と思われる最大の理由。
3.提言・行動・検証のサイクルを回す
提言をして終わりではなく、行動と検証をセットで進めることが重要です。
実践が伴わなければ、提言は「机上の空論」で終わってしまいます。
- 提言後は必ず「実行確認」と「結果検証」を行う。
- 動きが止まった場合は、あえて支援を一時中断する勇気も必要。
- 「行動する社長」には次の提案を、「迷う社長」には背中を押す助言を。
診断士の役割は、経営者を動かすきっかけをつくることです。
Ⅲ.コミュニケーションの技術を磨く
診断士にとって、最も重要なスキルは「話す力」ではなく「聴く力」です。
人は「理解された」と感じたときに、初めて相手を信頼します。

1.信頼を生む聴き方
- 前傾姿勢で聴く:「あなたの話を大事に聞いています」という姿勢を見せる。
- うなずき・表情:共感を示すリアクションが安心感を与える。
- フィードバック:「つまり〇〇ということですね?」と確認することで誤解を防ぐ。
- 沈黙を恐れない:相手が考える時間を尊重し、言葉を待つ。
コンサルティングの本質は「質問する力」と「聴く力」にある。
2.話すときの構成力
経営者は日々多忙です。
長い説明よりも、結論→理由→補足の順番で簡潔に伝えることが効果的です。
さらに、「短期提言」と「長期提言」を分けて提示することで、
経営者が優先順位をつけやすくなります。
聴く力を高める7つのポイント
- 1つ話したら、2つ聞く。
- 前傾姿勢でうなずく。
- 表情を明るく保つ。
- フィードバックで理解を確認する。
- 否定せず、肯定的に受け止める。
- 話の順序を整理し、結論から伝える。
- 相手が話しやすい雰囲気を意識的につくる。
「聞いてくれた人を人は好きになる」——これは経営者にも通じる普遍の心理です。
Ⅳ.学び続ける中小企業診断士であるために

1.ノウハウを隠さず共有する
知識を独占するよりも、公開しながら学ぶほうが成長がはやくなります。
他の診断士や専門家に話すことで、自分の理解が整理され、視野が広がります。
「話すことで学びが定着する」──これは教育学的にも証明されています。
2.挑戦が最大の学びを生む
やってみますと手を挙げて、それから猛烈に勉強します。
必要性が高まったときの方が身につきます。
完璧を求めて動かないより、やりながら吸収していく方が圧倒的にはやいです。
現場での「実戦学習」こそが、最強のトレーニングです。
3.経験の量が診断力を磨く
100社あれば100通りの提案がある。
財務分析やヒアリングだけでは見えない「現場のリアル」を感じ取る力は、経験によってしか身につきません。
- 現場を歩く:工場の音・社員の動き・空気感を観察
- 現場の声を聴く:経営者だけでなく、現場リーダーや従業員からも学ぶ
- 失敗を恐れず振り返る:何が通じ、何が響かなかったのかを記録する
経験は最大の教材。失敗は未来の提案の原材料になる。
4.ネットワークを広げる
税理士・弁護士・社労士などの専門家との連携は必須になってきます。
「この分野は○○先生に相談してみよう」と言える関係が、
信頼性と提案の幅を大きく広げます。
他士業との交流会や研究会に参加し、互いに紹介し合う仕組みをつくりましょう。
5.数字で語る力を鍛える
経営の本質は「数字の裏側を読み取ること」にあります。
P/L・B/S・C/Fの関係性を理解し、経営判断に落とし込む力を磨きましょう。
- 売上よりも「粗利率」や「キャッシュフロー」を重視
- 減価償却・在庫・借入金など、将来キャッシュを意識した提案
- 製造原価報告書を通じて、コスト構造を見抜く感性
「数字は会社の言葉」。それを正しく翻訳できる診断士でありたい。
Ⅴ.専門スキルという「武器」を持つ

中小企業診断士として活動していく中で、私は強く感じることがあります。
それは、中小企業診断士は「経営の知識だけでは足りない」ということです。
診断士としての視点は、企業の課題を発見するうえで非常に重要です。
しかし、その課題を「実際に解決する力」を持つためには、
もう一歩踏み込んだ「武器」となるスキルが必要です。
1.分析の次に必要なのは「実行支援の力」
診断士として多くの現場に関わる中で、
「分析まではできるけれど、そこから先の実行が進まない」ケースを何度も見てきました。
実際、企業が求めているのは「課題を見つけてくれる人」ではなく、
「成果を出すために伴走してくれる人」です。
そのため、経営分析だけでなく、
マーケティング・販売促進・デジタル活用などの「実践スキル」を身につけることが、
これからの診断士にとって大きな価値になります。
経営を「診る」だけでなく、「動かす」力が真のコンサルティング。
2.WEBマーケティングを学んだ理由
私は「経営者を支援するなら、売上づくりの現場にまで踏み込みたい」と考え、
WEBマーケティングを徹底的に学びました。
SEO・MEO・ホームページ制作・SNS・広告運用・アクセス解析など、
企業の売上を直接左右する領域を理解することで、
「経営改善の提案」が「実際の成果」へと結びつくようになりました。
数字と感覚の両面から経営を捉えることで、
提案の説得力や再現性が大きく高まりました。
「経営」と「マーケティング」は切り離せない。
売上の現場を理解してこそ、本質的な助言ができる。
3.株式会社CONVYとして独立した理由
こうした経験を重ねる中で、私は法人として
WEBマーケティング専門会社「株式会社CONVY」 を設立しました。
「共に(Con)+勝つ(vy)」の名の通り、
中小企業と共に勝利を目指す伴走型の支援を行っています。
経営分析のロジックを基盤に、
SEO・MEO・ホームページ制作・SNS・広告運用などの実行支援まで一貫して行うことで、
より確実な成果を出せるようになりました。
診断士としての知見 × WEBマーケティングの実行力
Ⅵ.キャリアは「偶然をつかむ力」で築かれる
1.計画的偶発性理論に学ぶ
米クランボルツ教授の「計画的偶発性理論」によれば、
キャリアの約80%は予期せぬ出来事によって形成されるといわれています。
最初から完璧なキャリア設計を描く必要はありません。
大切なのは、偶然のチャンスをつかむ準備をしておくことです。
私自身、会社員時代は財務とマーケティングの責任者として働いていました。
財務分析や中期経営計画、利益・資金シミュレーションなど数字の分野を得意とし、
「数字に強い診断士」として生きていくつもりでした。
ところが、独立後に中小企業を支援する中で気づいたのです。
「数字だけでは会社は良くならない」 ということに。
どんなに分析しても、売上が伸びなければ現場は変わらない。
そこから私は、経営のもう一つの柱である「WEBマーケティング」を徹底的に学び始めました。
SEO、MEO、広告運用、SNS運用、アクセス解析……。
経営者の想いを「成果」につなげるために、誰よりも現場を見て、試行錯誤を重ねました。
その結果、支援先の売上が実際に伸び、自社の事業も拡大。
やがて法人としてWEBマーケティング領域に特化した「株式会社CONVY」を設立するに至りました。
私自身も、予定していたキャリアを歩んでいるわけではありません。
しかし、偶然の出会いや気づきに全力で応えてきた結果、今の形が生まれました。
2.「山登り型」と「川下り型」キャリアの両輪
キャリア形成には、よく「山登り型」と「川下り型」という二つの考え方があります。
どちらもキャリアを進めるうえでの比喩的な表現で、
人によって、あるいは時期によってバランスが変わるものです。
山登り型は、明確な目標を定めて一歩ずつ登っていくタイプ。
キャリアビジョンを描き、計画的にスキルを積み上げていくスタイルです。
一方で、川下り型は、進むべき方向をおおまかに持ちながらも、
変化する環境に柔軟に対応し、流れに身を任せながら学びを得ていくスタイルです。
私はこの両輪が大切だと考えています。
目指す山を決めて努力することはもちろん重要です。
しかし現代は、将来の予測が難しい「VUCA(不確実・不安定・複雑・曖昧)」の時代です。
市場の変化は想像以上に速く、昨日の常識が今日には通用しないことも珍しくありません。
だからこそ、「山登り」のように努力と計画を積み重ねながらも、
「川下り」のように流れを読み、変化を恐れず方向を変えられる柔軟さが求められます。
山登りだけでは視野が狭まり、川下りだけでは目的を見失う。
大切なのは、二つのバランスを保ちながら、自分のペースで進み続けることです。
Ⅶ.まとめ:独立診断士に求められる5つの力
| 力 | 内容 |
|---|---|
| 人間力 | 信頼関係・共感・メンタリング |
| 専門力 | 戦略立案・財務分析・業界理解 |
| 提案力 | 現場を動かす具体策と行動支援 |
| 継続力 | 提言→実行→検証→再提言のサイクル |
| 学習力 | 学び続け、時代に適応する力 |
Ⅷ.おわりに
経営者を動かすのは、数字ではなく「人の心」です。
そして、経営者の心を動かすためには、診断士自身が成長し続ける必要があります。
「人を支える人」が自分を磨き続けることで、支援の質も深まっていく。
これからもこのブログでは、
現場で感じたこと、成功と失敗のリアル、学び続けるためのヒントを共有していきます。
経営やWEBマーケティングの支援にご関心のある方は、
株式会社CONVY(公式サイト) にもぜひお越しください。